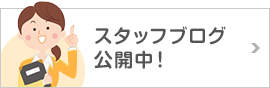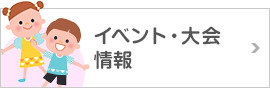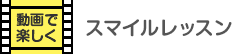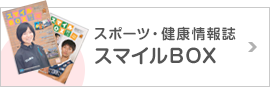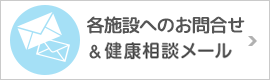皆さん、こんにちは
今回は「夏バテ防止策」の後編です。
お約束通り「土用の丑の日」について調べてみました
まず土用とは・・・
日本古来からある一年間を二十四等分した二十四節季のことで、日本独自の暦のことだそうです
特に二十四節季では補えない雑節のひとつで、立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間を指すそうです。その期間中の丑の日が「土用の丑の日」と呼ばれるそうです
ちなみに令和元年度の土用期間と丑の日は・・・
春の土用 4月17日(水)~5月5日(日)・・・4月22日(月)、5月4日(土)
夏の土用 7月20日(土)~8月7日(水)・・・7月27日(土)
秋の土用 10月21日(月)~11月7日(木)・・・10月31日(木)
冬の土用 1月17日(木)~2月3日(日)・・・1月28日(月)
「土用」には次のような言い伝えがありました・・・
この期間は、「土を司る神様」が支配する時期で、例えば、土用中に土を動かしたり、殺生をしてはいけない、また、丑の日には大根の種をまいてはいけない、葬送は延期しなければならないなどの習慣があったそうです
「土用」は季節の変わり目に当たります


そのため、農作業などの重労働で無理をすると、体調を崩しやすいので注意しましょう
という意味があるそうです
確かに農作業に限らず、季節の変わり目は誰もが体調を崩しやすくなるものですね~
だから、土用の期間中は無理をしないようにしよう、という昔の人の知恵なのでした(^_-)-☆
では、なぜ、土用の丑の日に鰻を食べるのでしょうか?
現在では、夏の土用の丑の日に鰻を食べることが、日本ではある意味、習慣化されていますね⁉
スーパーはもちろん、最近ではコンビニなどでも、「土用の丑の日にはうなぎを!」などと盛んに宣伝しています。
実は、土用の丑の日にうなぎを食べるようになった理由には、面白い由来があるんです!(諸説ありますが・・・)
時は江戸時代。夏になり、うなぎの売れ行きが悪くなって、困ったうなぎ屋さんが、蘭学者で発明家の「平賀源内」に相談しました。

相談を受けた平賀源内は、「丑の日には、「う」から始まる食べ物を食べれば、ばてることはない」という風習に習って、
店先に「「本日丑の日」という張り紙」をするようアドバイスしました。
その張り紙が功を奏して、鰻が飛ぶように売れるようになった、ということでした。
これをきっかけに、夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が始まり、現在まで引き継がれているのでした。
いかがでしたか?
私の夏バテ防止策は「餃子」「焼肉」「豚の生姜焼き」などなどしっかり食べること
しっかり睡眠時間を取ることを心がけています(^^)/
皆さんの夏バテ防止策を教えてくださいね~
よろしくお願いしま~す!!